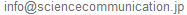第1回JASC定例会 開催概要
1.テーマ
広げよう サイエンスコミュニケーション その1
「サイエンスコミュニケーションの現状を語り合う」
2.開催概要
日時:2012年3月18日(日)13:30~16:00
会場:日本科学未来館 7階イノベーションホール
〒135-0064 東京都江東区青海2-3-6
http://www.miraikan.jst.go.jp/guide/route/
主催:一般社団法人日本サイエンスコミュニケーション協会
対象:サイエンスコミュニケーションに関心のある方ならどなたでも
※当日の様子はインターネット配信予定
配信機器トラブルのため、中継は中止しました。
当日の映像を掲載しました。以下の各プログラムを参照ください。
3.開催趣旨
一般社団法人日本サイエンスコミュニケーション協会(JASC)は、サイエンスコミュニケーションを促進することにより、社会全体のサイエンスリテラシーを高め、人々が科学技術をめぐる問題に主体的に関与していける社会の実現に貢献することを目的として設立されました。
本協会では、全国の広範な仲間との交流を通じて情報や理念を共有し、協働して課題を解決していくことを積極的に進めるため、定例研究会を開催します。
第1回~第3回定例研究会のテーマは「広げよう サイエンスコミュニケーション」です。全国で行われている多様なサイエンスコミュニケーションをつなぎ、点を線に、そして面にと広げていくことを目指します。
第1回定例研究会では、次の4項目をとりあげ、サイエンスコミュニケーションの現状について語り合います。
1)伝える 分かり易さvs専門性
2)サイエンスコミュニケーションで稼げるか?
3)サイエンスコミュニケーション研究とは?
4)身近なサイエンスコミュニケーションとは?
協会員でなくても、どなたでも自由に参加できますので、是非、ご参加のほど、よろしくお願いします。
4.プログラム
・開会 映像
・問題提起
| No | テーマ/概要 | 話題提供者 |
| 1 | 「伝える 分かり易さvs専門性」
サイエンスコミュニケーションとは一方的な講義ではなく対話することを指すとはいえ、科学を題材にする以上、コミュニケータは多かれ少なかれ科学について「伝える」必要があります。このとき、科学的知見を噛み砕いて話すことが非常に重要です。噛み砕くことで正確さは失われていくので、深い専門知識があるほど細かい齟齬に葛藤することになりますが、専門用語を多用しては聞き手はすぐに壁にぶつかってしまいます。細かいずれには目をつぶりつつ、大きな食い違いの無いよう、噛み砕く落としどころを模索しなければなりません。これと並んで大切なのが、コミュニケーション相手にどこまで求められているかを見極めることです。ただ平易な表現を使えば良いというものではありません。対象の年齢、興味の度合、知識の有無によって難易度は臨機応変に調節されるべきです。コミュニケーションの目的がどこにあるかも重要であると考えます。興味喚起なのか、ある程度の知識を定着させたいのか、科学的な思考方法そのものを会得して貰いたいのか――これは、サイエンスコミュニケーションとは何かという根本的な問題にも繋がると思います。相手の顔色を伺いながら、相手が求める程度の平易さで伝えてはじめて「分かり易く」伝えることになると考えます。
| 渡辺 洋津幾さん
(お茶の水女子大学大学院/国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータ) |
| 資 | JASC-workshop1-wtanabe.pdf | 映像 |
| 2 | 「サイエンス”コミュニケーション”は稼げるのか?」
近年サイエンスコミュニケーション(以下SC)分野で仕事を志す人が増えていますが、多くの方は「その様な仕事はない。」「稼げない。」という認識の人が多いと思います。そもそもSCで稼ぐ、儲けるという事は不可能なのでしょうか?今多くのSCと呼ばれる方々が、博物館や、企業研究機関広報、サイエンスライターとして活躍しており曲がりなりにもその仕事で生活をしていたりする訳なので実際に不可能だとは思えません。結局の所、我々はコミュニケーションというキーワードに振り回されていないでしょうか?コミュニケーションという単語自身が持つ、平等性、潔癖性の様なイメージなどによる理想論や自分がやりたい事が先行して、社会の大局的なニーズに答える事が難しくなっていたり、SC分野自身が世間や科学離れした所でから回っていたりしないのでしょうか?上記職業も「科学」という物に対する各地でのニーズを上手に組んでいるからこそ職業になっているという気がします。外部サブカルチャー系における科学系トークイベントの動きや料金設定、原発事故以降隆盛している「不安に寄り添う形」のSC、SC系を名乗る企業を紹介しながら、稼げるSCの方向とは何か?について考えてみたいと思います。
| 泉田賢一さん
(みけねこサイエンスプロジェクト/特定非営利活動法人発見工房クリエイト) |
| 資 | JASC-workshop1-senda.pdf | 映像 |
| 3 | 「サイエンスコミュニケーションに期待する研究とは」
科学コミュニケーションが一過性のものではなく、社会に本当に必要な活動として広がっていくには、研究もまた、必要でしょう。科学コミュニケーションの研究というと、理科教育やジャーナリズム、科学技術社会論の間に位置するテーマを思い浮かべられると思います。それらの研究は、科学コミュニケーションの中核として重要です。しかし日々、活動を行っている私たちには、さらに他の分野と協力することで、新しい研究を切り開いていくことができるはずです。これからは、コミュニケーションの実践と研究の両方を行う人材が必要です。会場では皆さんと一緒に、今後の科学コミュニケーションの研究の方向性について議論したいと思っています。
| 横山広美さん
(東京大学大学院理学系研究科)
|
| 資 | - | 映像 |
| 4 | 「身近なサイエンスコミュニケーションを発展させる秘訣とは?」
身の回りがサイエンスで囲まれているということは、「サイエンスコミュニケーション」も、色々なところに溢れていて、科学館スタッフや学校の先生などだけでなく、多くの方が様々な形で関わっているといえるでしょう。例えば、保健所の職員さん、ペットショップのスタッフさんなども含め、科学的な情報を一般の方に仲介する立場として活躍されている人はたくさんいます。ただ実際のところ、「サイエンスコミュニケーション」に深く関わっているのにもかかわらず、その大事な役目に気がついていない方も多いようです。いわば、“隠れサイエンスコミュニケーター”といえるでしょうか。多くの人が、「サイエンスコミュニケーション」自体について、そしてその重要性について改めて認識することができれば、社会において「サイエンスコミュニケーション」が発達する方向性がもっと見えてくるように思います。今回の研究会では、皆さんと一緒に、様々なところで見かける「サイエンスコミュニケーション」の存在をピックアップして再確認しながら、さらにどういった関わり方があるのか?発展的な活動をしたいと思ったときどうすればよいのか?具体的なスキルを磨く方法は?そして、それらをサポートする情報が得られる場所・環境を創っていくことの重要性について話し合いたいと思います。
| 内尾優子さん
(国立科学博物館研究推進課) |
| 資 | JASC-workshop1-uchio.pdf | 映像 |
・質疑応答 映像
・グループ・ディスカッション
・まとめ 映像(G1話題1)、映像(G2話題2)、映像(G3話題3)
5.お申し込み方法
EメールもしくはWebフォームよりお申し込みください。
・受付期間 2012年3月5日(月)12:00 ~2012年3月15日(木)12:00
参加は先着順です。(定員(120名)になり次第、期限前でもお申し込みを締め切りますのでご了承ください)
参加者には別途メールにて連絡差し上げます。
まだ席に余裕がございます。参加希望者はEメールもしくはWebフォームよりお申し込みの上、直接会場にお越しください。(事務局からの事前の確認連絡は致しません)
当日は4つのグループに分かれての分科会の時間がございます。
事前に、上記プログラム内容をご覧になってどの分科会に参加されるかご検討ください。
(当日、手を挙げていただいて、分かれることにしますが、多少の調整をさせていただくケースがあるかもしれません。ご了承ください。)
●Eメールでのお申し込み
Eメール(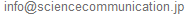 )宛てに、題名を「第一回JASC定例会申込」として、以下内容を記載してお申し込みください。
)宛てに、題名を「第一回JASC定例会申込」として、以下内容を記載してお申し込みください。
題名:第一回JASC定例会申込
--------------------------
[氏名]
[氏名よみがな]
[会員番号] ※会員の方のみ
[所属先名称]
[e-mailアドレス]
[連絡先電話番号]
--------------------------
●Webフォームよりお申し込み
本ページ下部にあるWebお申し込みフォームよりお申し込みください。
6.参加費
会員は無料、非会員は有料(学生500円、一般1000円)
7.問合せ先
一般社団法人日本サイエンスコミュニケーション協会 事務局
TEL:080-8257-7959 FAX:020-4622-7059
E-mail: